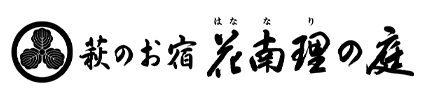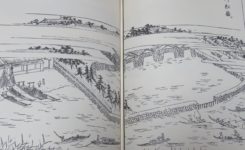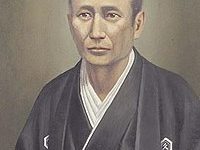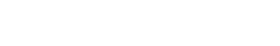今回は、大河ドラマ「花燃ゆ」で知られるようになった文(ふみ)のご主人楫取素彦を取り上げる。

素彦は文政十二年(1829年)、萩藩医松島瑞璠(ずいばん)の次男として現在熊谷(くまや)美術館のある魚棚沖(うおたなおき)町(現今魚店町)に生まれた。十二歳の時伊勢屋横町(現南古萩町)の小田村家に養子に入り、小田村伊之助を名乗る。養父が亡くなると中ノ倉に移り住む。
吉田松陰は素彦を高く買っていた。藩の仕事に多忙を極めた藩士の素彦と国禁を破った罪人である松陰では立場の違いはあったが、激しい尊王攘夷の思想の持ち主である点はかわりなかった。嘉永六年(1853年)吉田松陰の妹・寿(ひさ)は素彦と結婚するが、松陰の紹介ではないようだ。安政六年(1859年)松陰が野山獄から江戸に送られる時、幕府が朝廷に無断で条約を結んだ非を死をもって正す姿勢を示す「至誠にして動かざるは者未だ之れあらざるなり」という言葉を素彦に贈り、自分亡き後松下村塾の将来を託している。
禁門の変の敗北、第一次長州征伐の動きに長州藩は窮地に立たされる。藩内では幕府に恭順を示す勢力が台頭し素彦も斬首を覚悟する。さらに、第二次長州征伐の開始にあったっては、薩長同盟が結ばれていることを背景に幕府の命を拒み続け、素彦は幕府に監禁される。しかし、素彦はこんな絶体絶命のピンチを二度くぐり抜け、木戸孝允と坂本竜馬の間を取り持ち薩長同盟の締結に尽力するなど藩の重臣として大きな役割を果たす。
明治政府の下では、素彦は、明治七年熊谷(くまがや、現 群馬)県令に任命される。熊谷県は、現在の埼玉県の一部を含む八十五万石の大県だが、県民性は荒いものがあり県を治めるのは大変だった。しかし、素彦は松陰の「至誠」の心で県政を動かした。官営富岡製糸工場の存続に代表される伝統産業の養蚕・製糸業の振興を図る。また、養蚕の手伝いで小学校に行けない子どもが多くいた状況を克服し、全国一・二の就学率を誇る教育県を実現した。
なお、妻の寿が明治十四年に中風で亡くなると、寿の妹の文(松下村塾の高弟久坂玄瑞の妻、松陰の妹)と再婚する。

十二歳の時養子に入った伊勢屋横町(現南古萩町)の小田村家跡

養父が亡くなった時に移り住んだ中ノ倉の旧宅跡。

養父が亡くなった時に移り住んだ中ノ倉の旧宅跡。

最初の妻、吉田松陰の妹・寿(ひさ)

寿の妹の文(松下村塾の高弟久坂玄瑞の妻、松陰の妹)